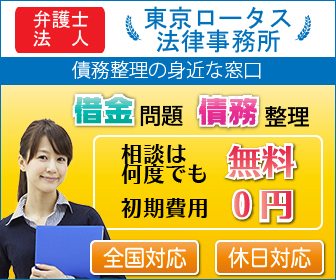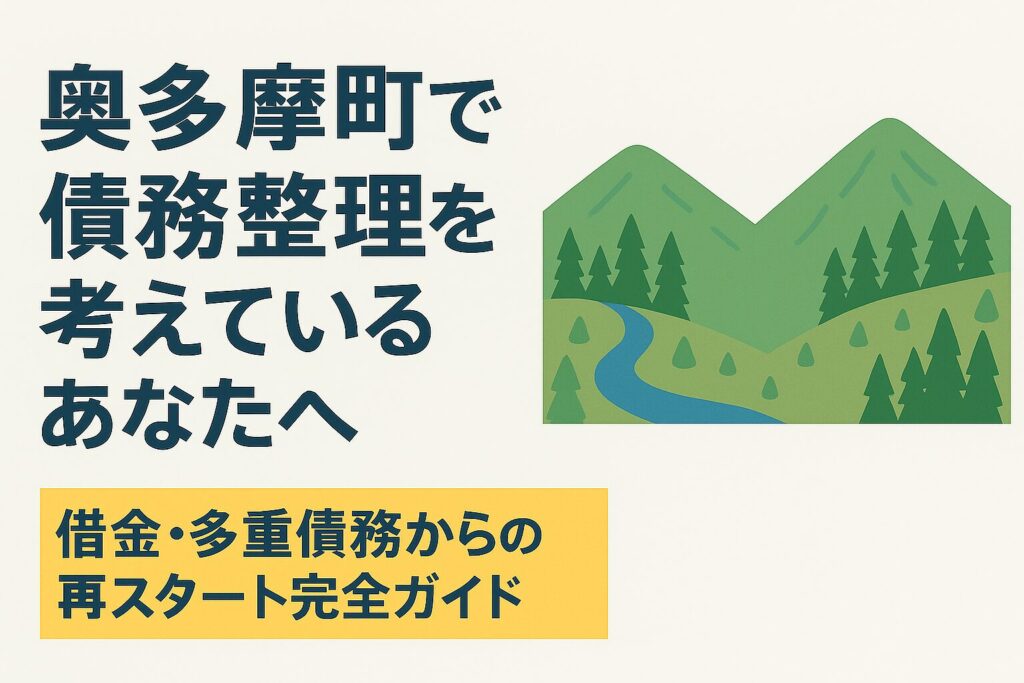
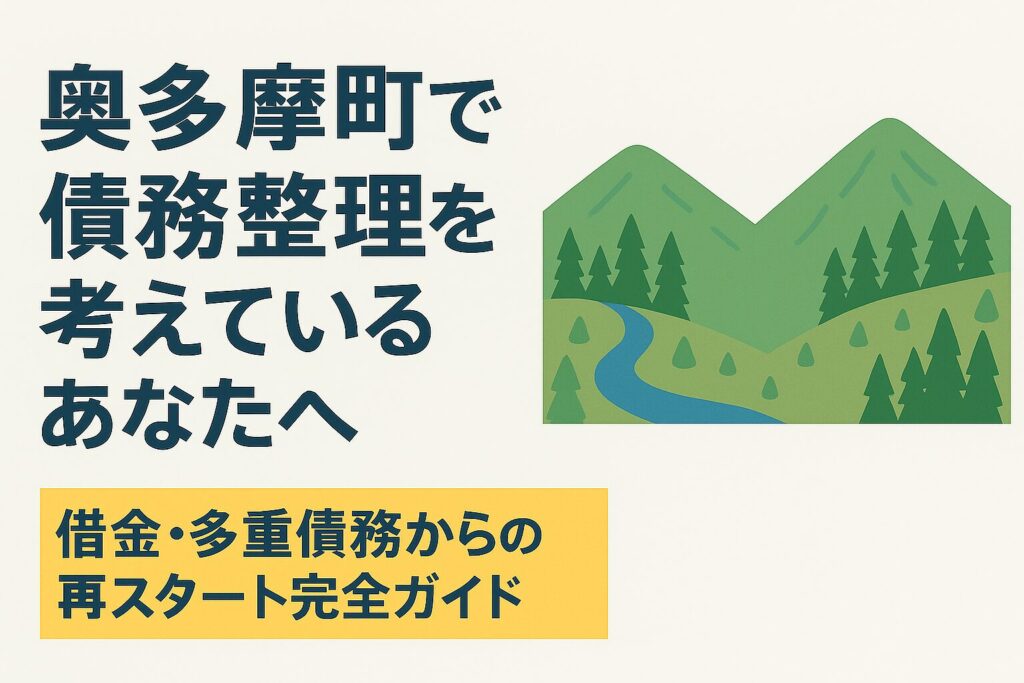
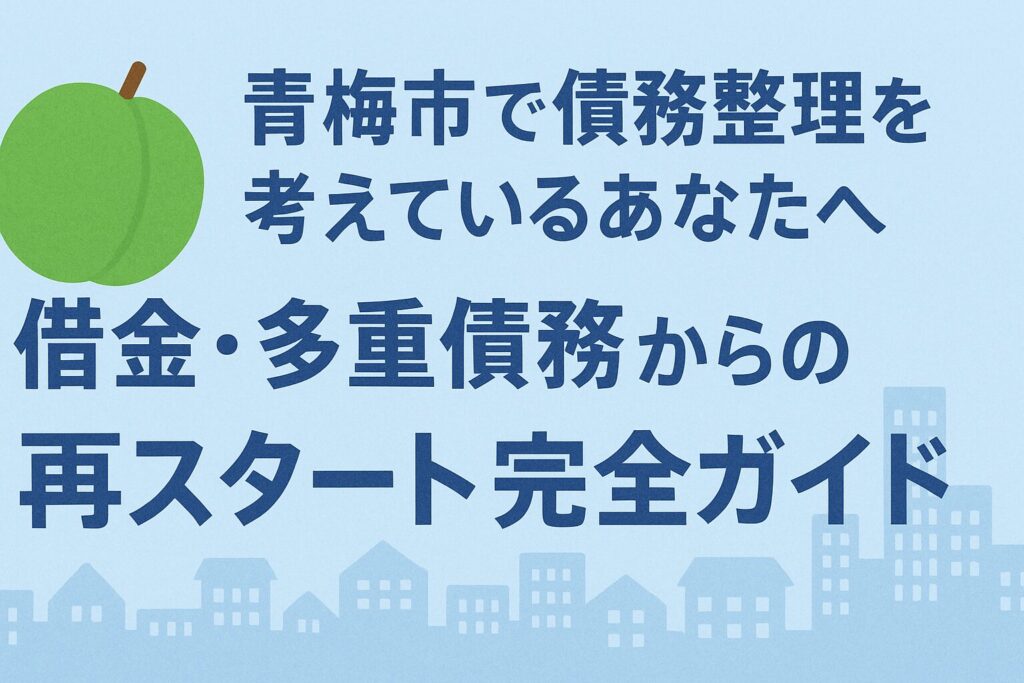
【青梅市で債務整理を考えているあなたへ】借金・多重債務からの再スタート完全ガイド
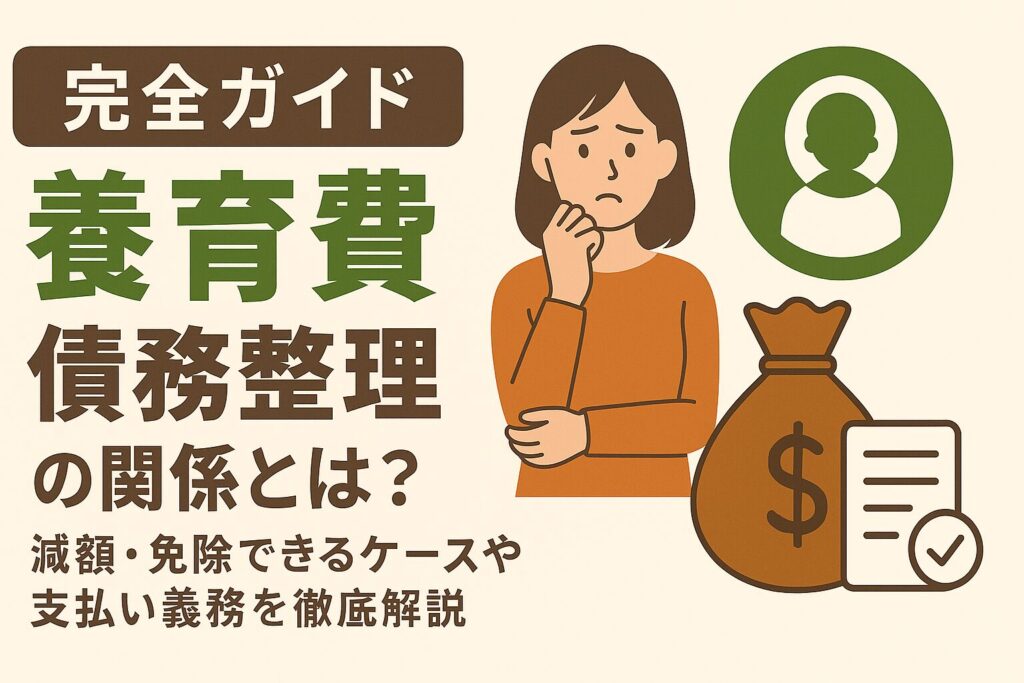
【完全ガイド】養育費と債務整理の関係とは?減額・免除できるケースや支払い義務を徹底解説

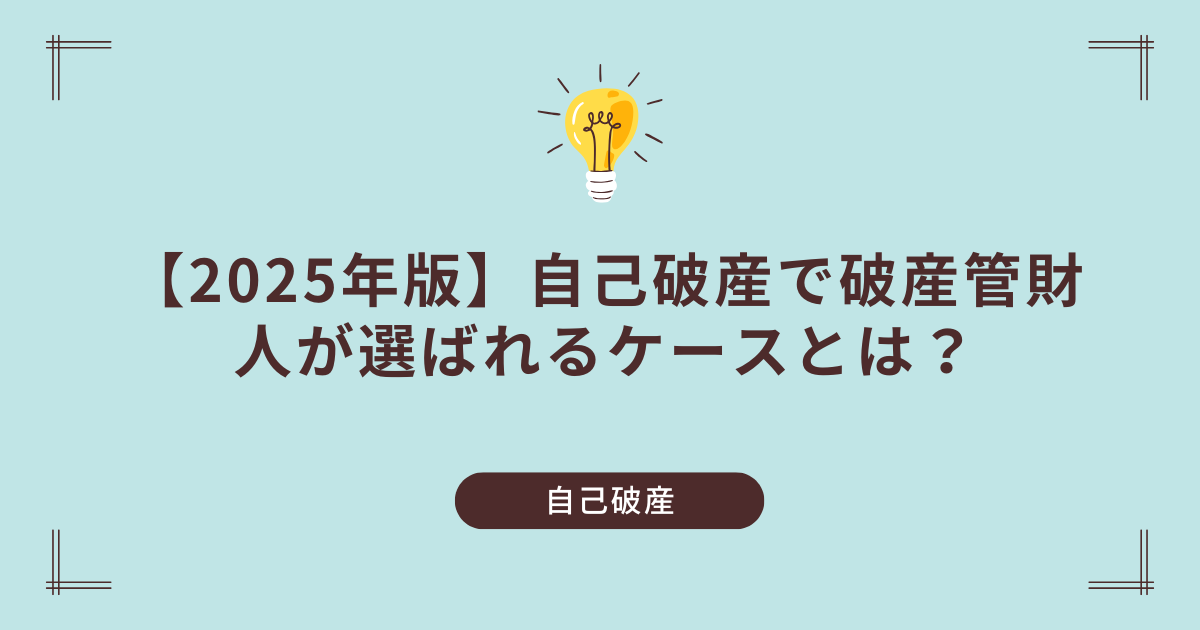
自己破産を検討している方の中には、「破産管財人って何?」「自己破産で破産管財人が選ばれるケースとは?」「自分のケースでは破産管財人が選ばれるの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか?
破産管財人は、自己破産の手続きを進めるうえで重要な役割を担う存在です。
本記事では、破産管財人が選ばれるケースやその費用、実際に選任された際の対応方法について、初めての方にもわかりやすく解説します。
自己破産を検討される方や現在自己破産を依頼中の方はぜひ最後までご覧ください。
📌債務整理におすすめの弁護士・司法書士事務所3選
弁護士法人ひばり法律事務所
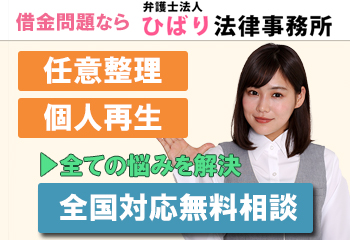
はたの法務事務所
東京ロータス法律事務所
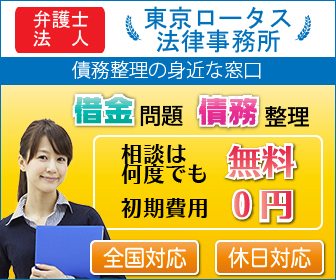
目次
自己破産の手続きを進めるなかで「破産管財人」という言葉を耳にすることがありますが、具体的にどのような存在で、どんな役割を担うのかについては、あまり知られていないかもしれません。
実際のところ、破産管財人は手続きの中で非常に重要なポジションを担っています。
まずは自己破産と破産管財人の関係についてわかりやすく解説していきます。
破産管財人の基本的な役割とは、自己破産手続きにおいて非常に重要な役割を担います。
その主な目的は、破産者の財産の調査・管理・換価処分、債権者への公平な配当の実現、免責不許可事由の調査です。
破産管財人は、破産者の財産が隠されていないか、過去に不正な取引が行われていないかを調査し、破産者の財産を売却処分します。最終的に破産者の財産が一定額以上になった場合には、債権者へ公平に配当を行います。
加えて、破産管財人は破産者に免責不許可事由(ギャンブルなどの浪費行為等)がないかを調査し、免責不許可事由が存在する場合には免責を許可しても良いかどうかの意見を述べます。
自己破産には「同時廃止」と「管財事件」という手続きがあります。それぞれ適用されるケースが異なります。
まず、「同時廃止」とは、①破産者に特に換価すべき財産がなく、②浪費行為などの免責不許可事由も存在せず、③破産者が事業者でない場合に適用されます。同時廃止の場合は早期に手続きが終了します。
一方、「管財事件」は破産者に一定以上の財産がある場合や浪費行為など免責不許可が存在する場合、破産者が事業者である場合に選ばれます。この場合、破産管財人が選任され、財産の管理・処分や免責調査が行われます。
例えば、会社員の方で財産がほとんどなく、浪費行為など免責不許可事由もない場合は原則として同時廃止として進みます。
逆に、一定金額以上の財産がある場合や浪費行為など免責不許可事由が存在する場合は管財事件となり、時間と費用がかかることがあります。
このように、財産状況や免責不許可事由などにより手続きの方法が決まるのです。
破産管財人が必要となるのは、自己破産の手続きを公正に進行するためです。破産者の財産を適切に管理し、債権者へ公平に配当する役割があります。
例えば、破産者が所有する不動産や高価な財産がある場合、破産管財人が財産を調査・処分し、債権者に分配します。これにより、全債権者へ公平な配当が実現されます。
破産管財人の存在により、破産手続きの透明性や債権者の平等性が図られます。
自己破産を申し立てる際、すべてのケースで破産管財人が選ばれるわけではありません。しかし、一定の条件に該当する場合には「管財事件」となり、破産管財人が選任されます。
ここでは、どのようなケースで破産管財人が必要になるのか、またその際に発生する費用や事前に備えておくべきポイントについて詳しく解説します。
自己破産が「管財事件」となる場合には以下のような基準があります。
これらの一つでも該当する場合は原則として管財事件となり、全てに該当しない場合は同時廃止となります。
管財事件は、債務者に一定額以上の換価すべき価値のある財産がある場合に選ばれます。この財産には、現金や預貯金、保険解約返戻金、有価証券(株・投資信託・出資金等)、退職金、自動車、不動産など換価可能な全ての財産が含まれます。
この「一定額」とは、裁判所によって基準が微妙に異なります。もっとも、例えば東京地裁では、預貯金や保険解約返戻金、有価証券(株・投資信託・出資金等)、退職金の8分の1の金額、自動車、不動産などの財産が20万円を超える場合には管財事件となります。
以下のような免責不許可事由がある場合、原則として管財事件となります。
自己破産で避けるべき偏頗弁済とは?バレた時のリスクや対処法を解説
【自己破産とキャリア決済】バレた場合のリスク&安全な対処法7選
破産者が個人事業主の場合には原則として管財事件となります。
破産管財人が選任される場合、債務者(自己破産を申し立てた人)は「管財予納金」という費用を裁判所に納める必要があります。
東京地裁や横浜地裁、さいたま地裁、千葉地裁など都市部の裁判所では、原則として20万円が目安とされています。一方で、地方の裁判所では30万円〜50万円程度を求められるケースもあり、管財予納金には地域差があります。
破産管財人が選任された場合、債務者の生活には一定の制限や影響が出ることがあります。ただし、これは破産手続きを適切かつ迅速に進めるために必要な措置であり、債務者の権利を不当に制限するものではありません。
破産管財人の第一の任務は、債務者が保有している財産を調査し、必要に応じてそれを換価・処分することです。
これには以下のような財産が含まれます:
換価された財産は、債権者に対して公平に配当されます。
破産管財人は、債務者に免責不許可事由があるかどうかを詳細に調査します。これは借金を帳消しにするか否かの判断に関わる極めて重要なポイントです。
具体的には以下のようなケースが該当します:
ただし、免責不許可事由があっても、誠実な対応をしていれば「裁量免責」として借金の免除(免責)が認められる場合もあります。
破産手続き期間中、破産管財人は債務者に届く郵便物を一時的に受け取ることが認められます。これにより、財産や取引に関する重要な情報を把握することができます。
また、債務者が転居する場合には、破産管財人の許可を得る必要があります。これは連絡の行き違いや調査の妨げを防ぐための措置です。
破産手続きの中で、破産管財人と面談を行うことがあります。この面接では、財産状況や借金の経緯、支出の詳細などが確認されるため、事前準備が欠かせません。
面接に際しては、以下のような資料を準備しておくと良いでしょう:
また、心構えとしては、誠実かつ正確に答えることが重要です。嘘や隠し事は調査の長期化や免責不許可のリスクを高めます。
破産管財人は債権者の利益を保護する立場ではありますが、同時に破産者の再出発を妨げないよう配慮された存在でもあります。
そのため、誠実に情報を開示し、協力する姿勢を見せることが、手続きの円滑化と免責許可への近道となります。
自己破産の手続きにおいては、弁護士に依頼するかどうかが大きな分岐点となります。特に、破産管財人が選任される可能性があるケースでは、弁護士のサポートが極めて有効です。
弁護士に依頼することで、煩雑な書類の作成や提出手続きを正確かつ迅速に行うことができます。書類不備や誤記載は手続きの遅延や不利益につながる可能性がありますが、弁護士がいればそれを未然に防ぐことができます。
破産管財人との連絡や面談の日程調整、質問対応なども弁護士が代行してくれるため、債務者の精神的・時間的負担を大きく軽減することができます。経験豊富な弁護士であれば、よく聞かれる質問や対応のポイントを事前に助言してくれます。
弁護士に依頼して自己破産を行う場合、通常の管財事件よりも手続きが簡略化された「少額管財事件」として取り扱われることが多く、管財予納金も20万円前後に抑えられることが期待されます。
これは裁判所による運用上のメリットであり、申立てを円滑に進める手段として活用されています。
ここでは、破産管財人が選任された場合によく寄せられる質問とその回答をまとめてご紹介します。
A. はい、通常は同時廃止事件に比べて2〜4か月程度長くなる傾向があります。破産管財人が財産調査や免責調査を行うため、一定の時間が必要となります。
ただし、必要書類の提出を怠らず、誠実な対応を心がけることで、手続きの進行を妨げることなく進めることが可能です。
A. 家族に関しては、同居していればある程度情報が伝わる可能性が高いです。郵便物の確認や財産状況の申告などの場面で知られることがあります。
また、職場から退職金額に関する資料を提出する必要があるため、その際に職場に知られる可能性があります。
A. 通常管財事件では、調査項目や処理が多いため、手続きが煩雑で費用も高くなります(予納金50万円以上)。
一方、少額管財事件は弁護士が関与しており、破産管財人の作業が比較的簡素化されている場合に適用されます。費用は20万円前後で手続期間も短縮されることがあります。
破産管財人が選任されるかどうかは、財産の有無や借金の理由(免責不許可事由の有無)などに大きく左右されます。選任された場合は、破産管財人の指示に従い、誠実な対応を行うことが何よりも大切です。
自己破産という選択が再出発の第一歩となるように、まずは一歩踏み出して弁護士や司法書士へ相談を行ってみましょう。
📌債務整理におすすめの弁護士・司法書士事務所3選
弁護士法人ひばり法律事務所
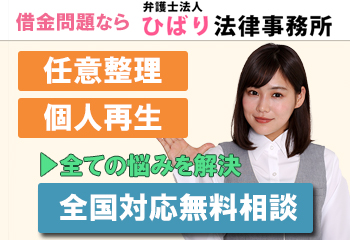
はたの法務事務所
東京ロータス法律事務所