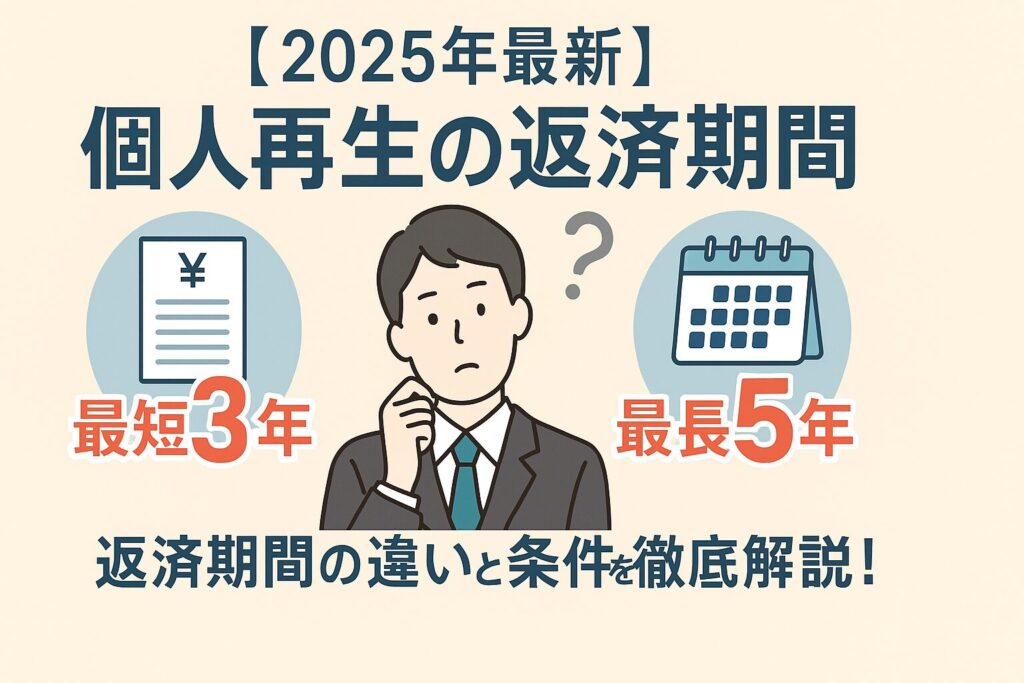
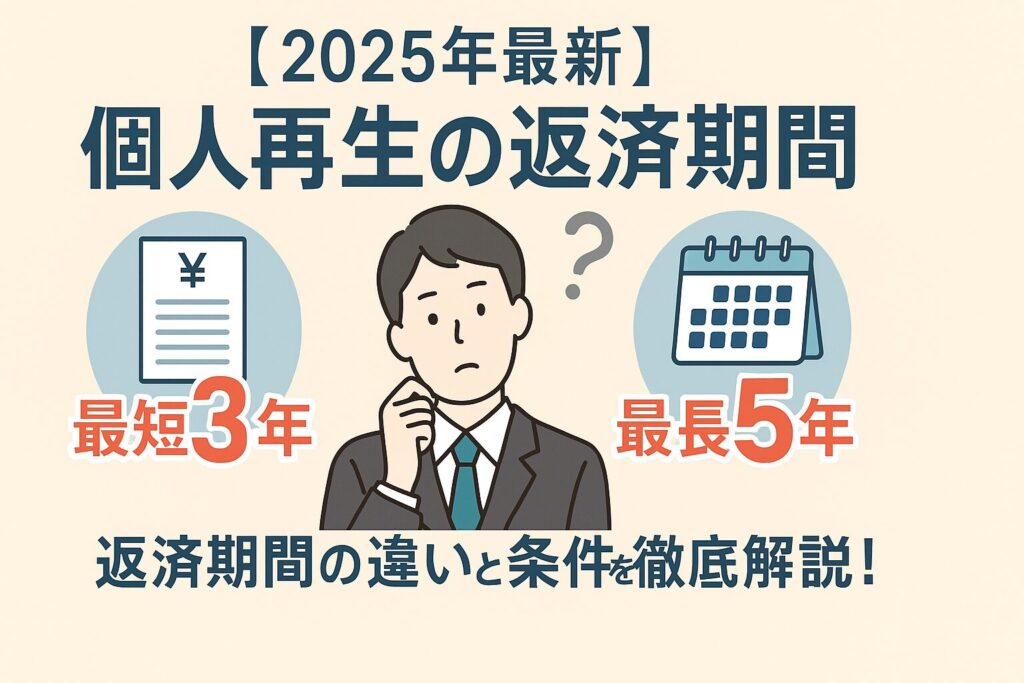
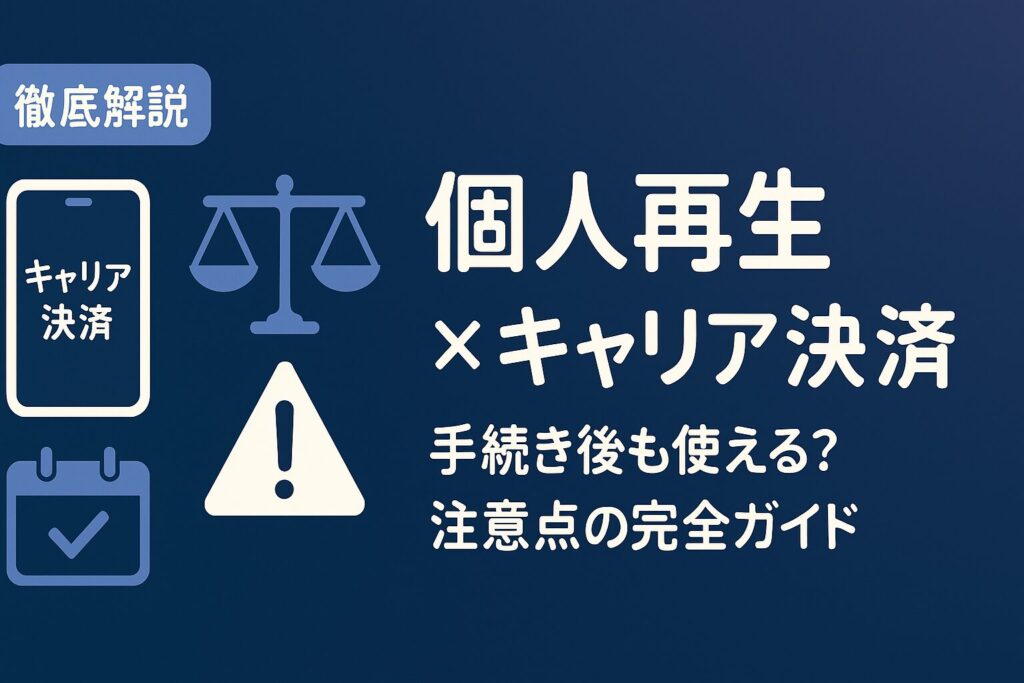
【個人再生×キャリア決済】手続き後も使える?注意点の完全ガイド
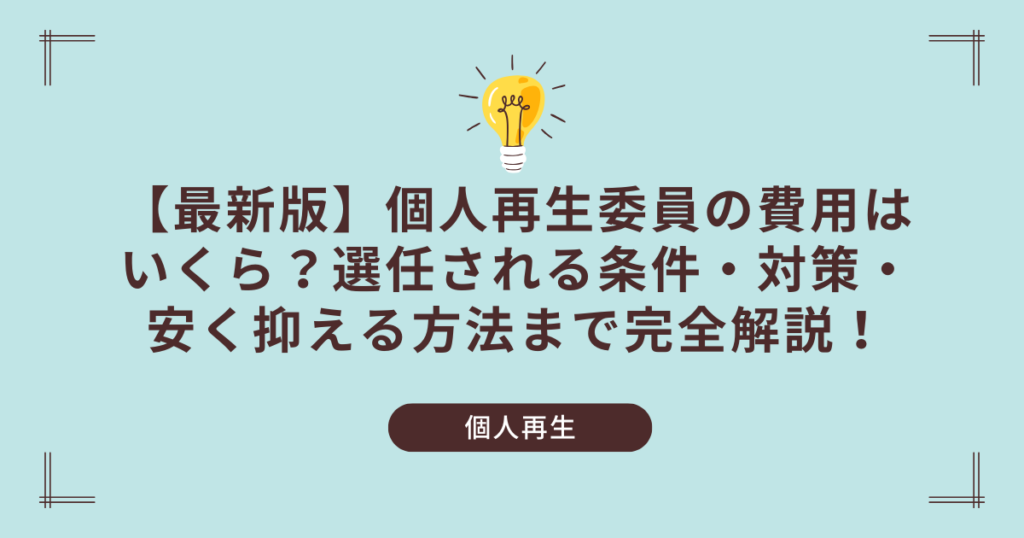
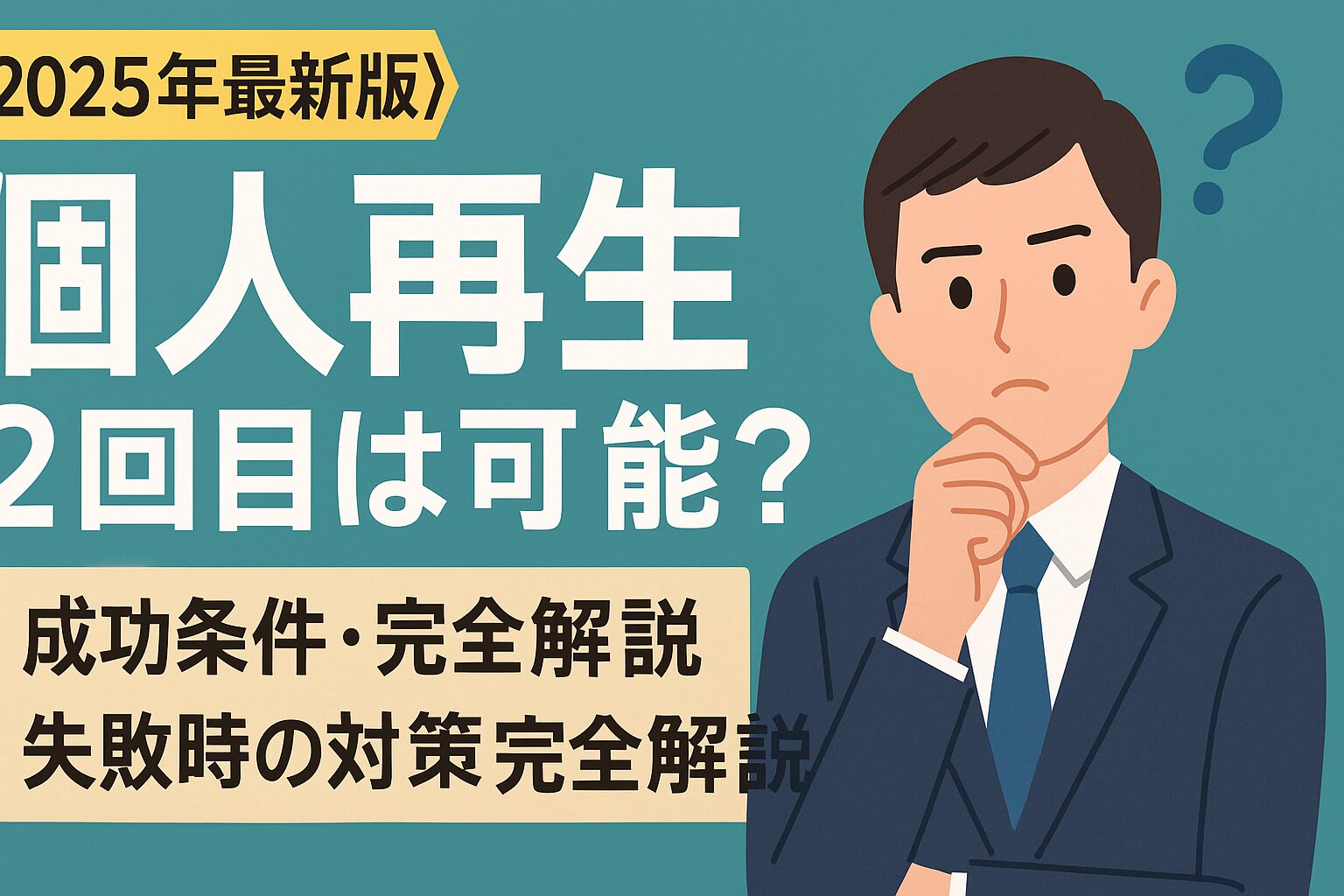
個人再生は債務整理のひとつであり、借金を大幅に減らし、返済計画を立てて生活を再建する制度です。
過去に1回個人再生を行った場合でも、事情によっては 再度の個人再生(2回目) が可能なケースがあります。
この記事では、2回目の個人再生を検討している方に向けて、以下の内容を網羅的に、わかりやすく解説します
これから2回目の個人再生を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
まず結論として、法律上は 2回目以降の個人再生は禁じられていません。
つまり、過去に個人再生を利用したとしても、条件を満たす限り再度の個人再生は可能です。
ただし、「何度でも自由にできる」というわけではなく、個人再生の種類や手続きや前回の個人再生からの経過期間、前回の個人再生の結果・経過状況が再度の個人再生が認められるか否かに影響を与えます。
個人再生には次の2つの種類があります。
小規模個人再生:個人事業主を含め、収入がある方すべてが対象です。ただし、債務総額(住宅ローンを除く)が 5,000万円以下 であり、将来にわたって継続的に収入を得る見込みがあることが要件です。
給与所得者等再生:会社員、公務員など安定的な給与収入がある者が対象です。加えて、定期的な収入かつ収入の変動幅が小さいことも要件として求められます。
この2つの手続きは、2回目の個人再生を行う場合も重要なポイントになります。なぜなら、小規模個人再生か給与所得者等再生かによって2回目の個人再生に対する制限や要件が異なるためです。
2回目の個人再生を考える際には、前回の個人再生からどのくらい期間が経過しているかが重要な判断材料となります。
具体的には、前回が給与所得者等再生だった場合、再生計画の認可決定確定日から 7年間 を経過していないと、再度の給与所得者等再生ができないという規定があります。
一方、前回が 小規模個人再生 だった場合は、2回目が小規模個人再生であっても給与所得者等再生であっても、特に期間制限はありません。
そのため、前回給与所得等再生を行った方が再度の給与所得等再生を行う場合、前回の個人再生から7年間は期間を空ける必要があります。
2回目の個人再生では、1回目よりも厳格なチェックが入るケースが多いです。以下、主な注意点を整理します。
1回目と同じような理由・経緯で2回目の個人再生を行った場合、裁判所から、前回から生活改善がなされていないと判断され、2回目の個人再生を認めてもまた債務を増やすのではないかと疑われます。そのため、今後の返済能力や生活改善策をより厳しくチェックされます。
2回目の個人再生では裁判所からのチェックも厳しくなるため、申立書類(収入証明、財産状況の添付資料、陳述書における借入の経緯)はより詳細に準備しなければならず、結果的に認可決定まで時間がかかったり、認可がなされないリスクが高まります
小規模個人再生では、総債権者の過半数、または債務総額の半分以上の債権者が小規模個人再生に反対すると個人再生は認められません。
1回目と2回目で同じ債権者が存在する場合、その債権者は反対意見を出す可能性があります。
債権者からすれば、「個人再生を認めてもまた借入を行って返済ができなくなるのではないか」「なぜ再び借金が膨らんだのか」という疑問が生じやすく、債権者が反対する可能性が高まります。
個人再生の手続きでは、最低返済額・清算価値・可処分所得額という基準があり、その基準によって個人再生における弁済総額が決まります。
小規模個人再生では、最低弁済額と清算価値の基準額のいずれか高い方の金額が個人再生における弁済総額になります。そして、最低弁済額とは債務総額に応じた基準(例:債務額500万円以下なら100万円、債務額500万円以上1500万円以下なら5分の1の額、債務額1500万円~3000万円なら300万円、債務額3000万円~5000万円なら10分の1の額)です。また、清算価値とは債務者のすべての財産を処分した場合の合計金額を指します。
さらに、給与所得者等再生では、最低弁済額や清算価値の基準に加え、可処分所得額の基準もあります。具体的には、可処分所得額(収入から税金・社会保険料・最低生活費などを差し引いた額)の2年間分以上の金額を個人再生における弁済総額とする必要があるというものです。
そのため、1回目の個人再生後に新たに財産が増えた場合(清算価値が増加した場合)や1回目の個人再生より負債額が多い場合(最低弁済額の増加)、1回目の個人再生より収入が増加した場合(可処分所得の増加)には、1回目の個人再生よりも返済額が増加することがあります。
万一、2回目の個人再生が認可されなかった場合には、他の債務整理手段を検討する必要があります。
任意整理は、裁判所を介さず債権者と直接交渉を行い、利息のカットや毎月の返済額の減額といった返済条件を見直す手続きです。
任意整理は手続きが比較的スムーズで柔軟な対応ができます。また、個人再生と比較して費用も安く済みます。
もっとも、任意整理では元金の減額はまずできないため、元金を大幅に減額できる個人再生よりも毎月の返済額や返済総額は多くなります。
自己破産は、支払能力が極めて低い場合において、裁判所を介して債務の全額免除(税金や養育費など一部免除されない債務もあり)を受ける手続きです。
個人再生では返済が困難な場合には、自己破産を検討する選択肢になります。
ただし、自己破産では一定額以上の財産が処分され、借金の理由(ギャンブルなど浪費行為等)によっては債務の免除が認められない場合も稀にあります。
2回目の個人再生が認可されなかった原因を整理し、以下のような対策を講じることが重要です:
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| 失敗原因の分析 | 前回の個人再生でなぜ認可が得られなかったのかを専門家と振り返る。 |
| 収入・家計の改善 | 安定収入の確保や支出の見直しを行い、再度の個人再生申立時に改善後の状況を示す。 |
| 個人再生以外の手段の検討 | 収入や支出の見直しによっても個人再生が難しいと考えられる場合には、任意整理や自己破産など個人再生以外の手段を検討する。 |
過去に債務整理歴(任意整理、個人再生、自己破産など)があると、2回目の個人再生に影響する可能性があります。
任意整理を行った後、返済が難しくなり個人再生に切り替えるケースは多々あります。任意整理後でも個人再生申立ては可能ですが、任意整理でなぜ返済ができなくなったのか、そもそも任意整理を行うことは適切だったのかについて裁判所からチェックされます。
特に、任意整理において一部の債権者だけ任意整理を行っていた場合、任意整理を行っていない債権者(利息を含め通常通り返済していた債権者)と任意整理を行った債権者(利息をカットしてもらい返済していた債権者)の間で不公平さが生じます。そして、裁判所から、任意整理を行っていない債権者を害する目的で一部の債権者についての任意整理を行ったと判断された場合、個人再生が棄却(認められない)されることがあります。
自己破産後でも個人再生は申立ては可能です。ただし、給与所得等再生の場合は免責決定確定から7年を経過しなければ行うことができず、経過期間も重要となります。
また、自己破産を行った後に再度借金を増やした理由がギャンブルなど浪費行為の場合には、自己責任であると判断され、より審査が厳しくなります。
そのため、家計管理や収入改善、借入理由の説明が重要になります。
個人再生の手続きを行う場合、手続き開始後の借入は禁止されています。それにもかかわらず個人再生の手続き中(認可決定前)に新たな借入をすると、裁判所や債権者から「返済の意思がない」「返済見込みがない」と見なされ、個人再生が認められない可能性が高まります。
安定的な収支状況を示すためには、返済中は借入を絶対に避け、収支の改善策を裁判所に示すことが重要です。
はい。2回目の個人再生では提出する書類が増え、借入の経緯もより詳細な説明が必要となりますので、1回目の個人再生より手続きに時間がかかることがあります。
また、提出書類が増え、手続きの難易度も高くなりますので、弁護士・司法書士に支払う費用も増額となる場合があります。
弁護士・司法書士に相談する際は、以下の情報をできるだけ正確かつ詳細に伝えることが重要です
| 内容 | 伝えるべき情報 |
|---|---|
| 過去の債務整理 | 手続きの種類(任意整理、小規模個人再生、給与所得者等再生、自己破産)や手続きを行った時期 |
| 負債状況 | 借入先会社名、借入先ごとの負債額、返済期間 |
| 収入・支出 | 現在の収入、家族構成、毎月の支出額、今後発生する大きな支出 |
| 借入理由 | 病気、失業、子供の教育費、浪費癖など、借金が膨らんだ経緯を時系列で詳細に説明 |
| 財産状況 | 預貯金、保険、自動車、退職金見込み額、有価証券、不動産等 |
弁護士・司法書士に正直かつ詳細な情報を共有することで、スムーズかつ正確な個人再生手続きが可能です。隠し事やうそは個人再生の失敗リスクを高めるため避けましょう。
借入理由によっては断られる可能性もあります。
もっとも、これまでの経緯を正直に伝え、誠実な対応を行えば2回目の個人再生であっても依頼を受けてもらえる事務所はそれなりにあります。
2回目の個人再生を成功させるには、適切な準備と戦略が重要です。以下は具体的なステップとポイントです。
前回の個人再生から何年経っているか確認(給与所得者等再生なら7年以上が目安)。
借金が再び増えた理由を整理(時系列で細かくまとめる)。
家計改善や収入改善を行ったことを示す。
現実的な返済計画:3年返済が通常ですが、特別の事情があれば5年に延長されることもあります。
債務額・返済回数:負債総額を前提に個人再生による弁済総額を算出します。
弁護士や司法書士に相談し、借入経緯や資料を提出して個人再生を依頼する。
特に2回目の個人再生は1回目の個人再生より慎重な対応が求められるため、個人再生を得意とする弁護士・司法書士への依頼は重要です。
以下は典型的なケースと、成功例・失敗例を整理したものです。
| ケース | 成功パターン | 失敗パターン | 対策ポイント |
|---|---|---|---|
| ケース A(1回目小規模 → 2回目小規模) | 前回完済後、失業など不可抗力による借入れ →返済見込みあり。 | 債権者による反対で再生計画案の否認。 | 債権者との調整を丁寧に行い、返済能力を示す。 |
| ケース B(1回目給与所得者等 → 2回目給与所得者等) | 前回から7年以上経過、安定収入あり。返済計画が認められた。 | 前回から7年未満 →却下。 | 7年未満の場合は小規模個人再生を検討する。 |
2回目の個人再生を行う場合、1回目の個人再生よりも多くの注意点や条件があるため、事前の正確な情報収集が大切です。
不安な点を一つずつ整理し、適切な手続きを踏むことで、再スタートのチャンスを広げられます。
再度の債務整理を検討している方は、弁護士・司法書士への早めの相談をおすすめします。